INNOVATIONイノベーション
無線機器や無線通信に関する基礎技術から最先端研究まで、
さまざまな情報を提供します。
グローバルワイヤレスソリューション企業として成長し続けるべく、オープンイノベーションなどを通して精力的に新しい分野の研究開発にも挑戦しています。


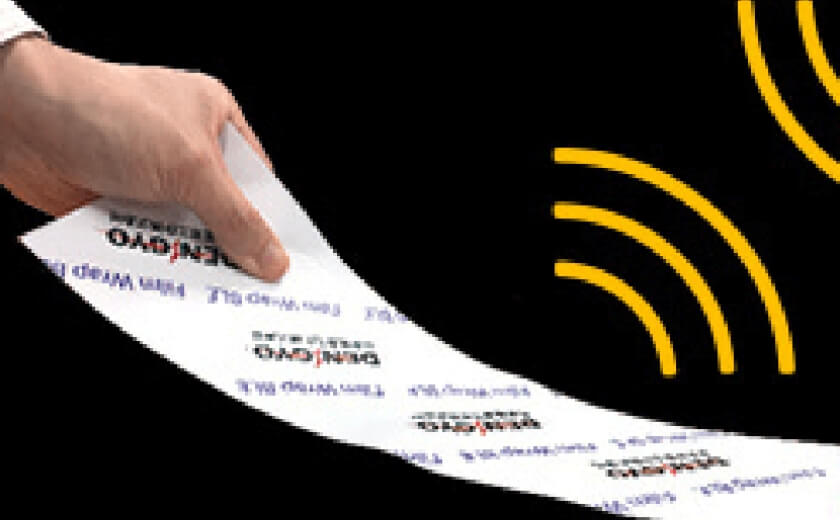

無線通信に必要な無線装置の構成および基本技術について解説します。

アンテナなど主力製品の開発工程をはじめ、電波技術の最先端の研究現場などをレポートします。